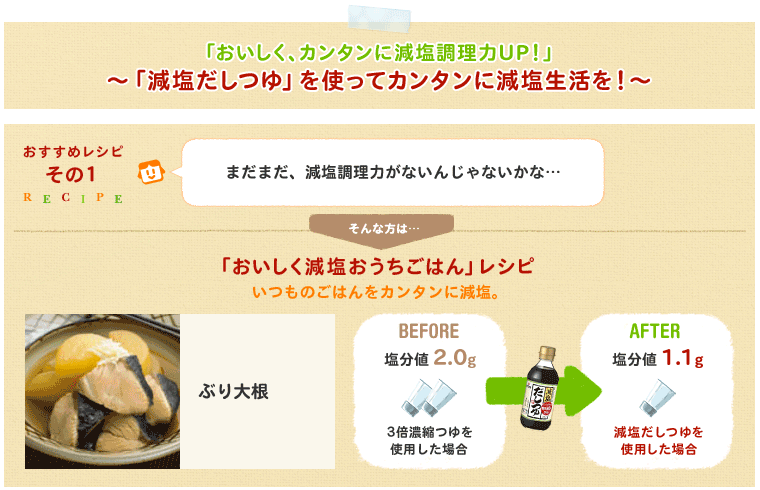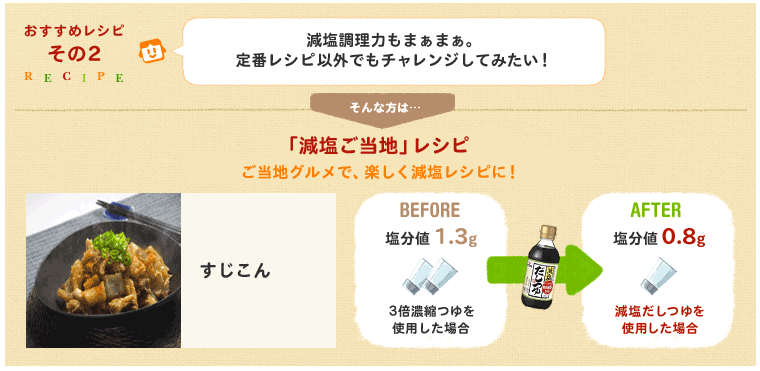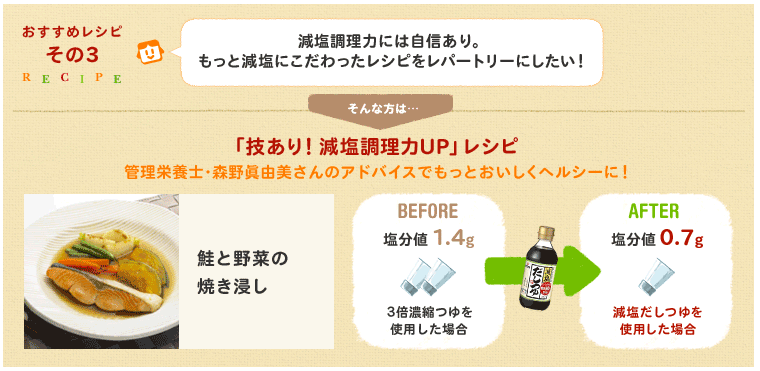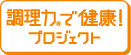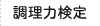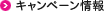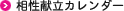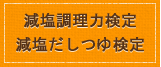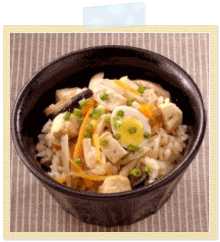
健康のためには塩分を減らしたいけれど、どんな工夫をしたらいいの?
これまでに2000人以上の方がチャレンジしてくれた「減塩調理力検定」。
なんとカロリー検定に次いで2番目に多い受験者数(健康テーマ検定 2010年9月1日~2010年12月18日)で、みなさんが日頃から減塩に高い関心を持っていることがわかりました。
また、キャンペーンアンケートの結果からも、減塩に対するみなさんの努力と理解度が明らかに! その結果を報告します。
これまでに2000人以上の方がチャレンジしてくれた「減塩調理力検定」。
なんとカロリー検定に次いで2番目に多い受験者数(健康テーマ検定 2010年9月1日~2010年12月18日)で、みなさんが日頃から減塩に高い関心を持っていることがわかりました。
また、キャンペーンアンケートの結果からも、減塩に対するみなさんの努力と理解度が明らかに! その結果を報告します。


「減塩調理力検定」は、主に30~50代の主婦が受験してくれました。
検定受験者を対象にしたアンケートで「減塩はどなたのためにしていますか?」と質問したところ、 約80%の人が自分のため、約54%が夫のためという人でした。
年代的にも塩分のとりすぎが原因となる高血圧を気にしている様子がうかがえます。
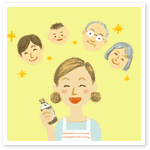
多くの人が自分や家族のために減塩をしているようですが、実は「減塩調理力検定」の正解率の平均は68%。
これは調理力検定全体の平均74%よりも低めの、ちょっぴり塩味のきいた(=しょっぱい)結果です。
みなさんは何点とれましたか?

検定結果をよーく見てみると正解率の低い問題が4問あることが分かりました。
この4問の共通点を分析してみると、どれも塩分の量に関するものでした。
例えば「Q1 日本人の塩分摂取量(食塩相当)はどのくらい?」という問題。
答えは約11g(平成20年国民健康・栄養調査結果による)で正解率は50%以下でした。
この問題では、3割以上の人が11g以下の数値を回答。
この結果から「減塩をしているつもり」でも、塩分はとりすぎの傾向にある現状が表れたのかもしれませんね。
この4問の共通点を分析してみると、どれも塩分の量に関するものでした。
例えば「Q1 日本人の塩分摂取量(食塩相当)はどのくらい?」という問題。
答えは約11g(平成20年国民健康・栄養調査結果による)で正解率は50%以下でした。
この問題では、3割以上の人が11g以下の数値を回答。
この結果から「減塩をしているつもり」でも、塩分はとりすぎの傾向にある現状が表れたのかもしれませんね。
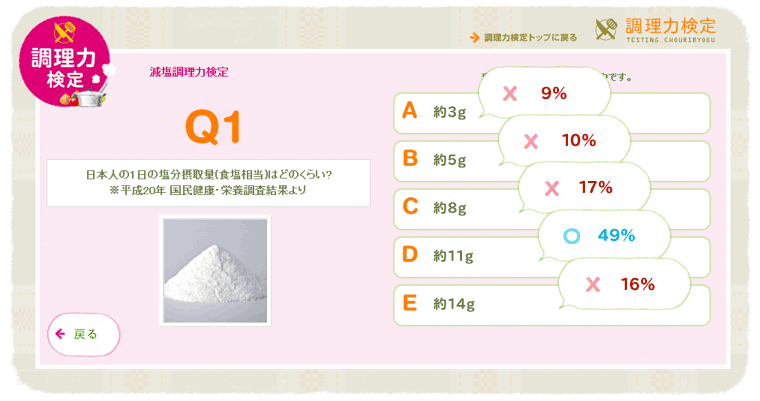
※各選択肢を回答した人の割合
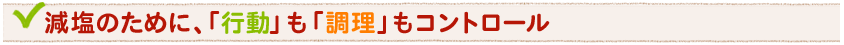
検定を受験した皆さんへ、アンケートで「減塩について気をつけていることがあれば教えてください」という質問をしてみました。
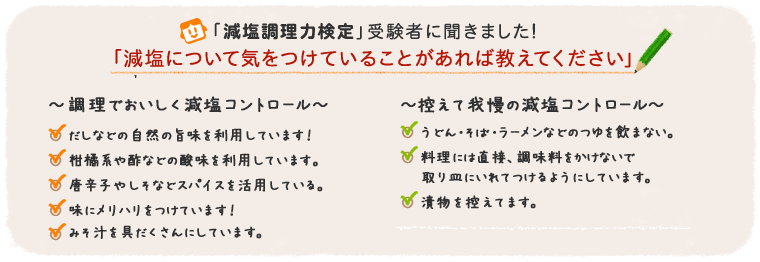
みなさん、減塩のために調理でコントロールしたり我慢したりと、いろいろとがんばっていますね!
塩分は単純に減らしてしまうと甘味もうま味も引き立たず、物足りない料理になってしまいますが、うま味や酸味を利用しておいしい減塩をしているようです。
さらにもう一歩、減塩生活をステップアップさせるにはどうしたらいいのでしょう?
塩分は単純に減らしてしまうと甘味もうま味も引き立たず、物足りない料理になってしまいますが、うま味や酸味を利用しておいしい減塩をしているようです。
さらにもう一歩、減塩生活をステップアップさせるにはどうしたらいいのでしょう?

ヒントは減塩調理力検定の中にありました。
同検定に「おでんのネタ、次のうちもっとも塩分が多いのは?」という問題があったのを覚えていますか?
そう、減塩のポイントは食品自体に含まれる「見えない塩分」にあるのです。
同検定に「おでんのネタ、次のうちもっとも塩分が多いのは?」という問題があったのを覚えていますか?
そう、減塩のポイントは食品自体に含まれる「見えない塩分」にあるのです。
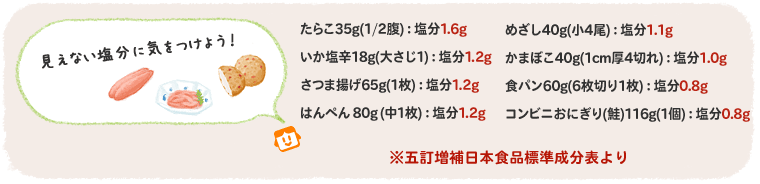
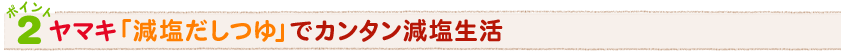
塩分摂取の目標量が男性は9.0g未満、女性は7.5g未満で、しかも日本高血圧学会では1日6g未満をガイドラインとしています。
ちょっとハードルが高い気がしますね。
でも大丈夫。定番のおうちごはんの中で塩分が高くなりがちなメニューでも、「減塩だしつゆ」を使えばカンタンに減塩ができます。
しょうゆ代わりにお浸しや冷奴にかけるだけでも減塩に。もちろん、煮物や炒め物にも幅広く使えます。
かつおだしのうま味がきいているので、我慢することなく調理の工夫で、満足感を得ながらおいしく減塩ができるのです。
おいしくカンタンなことから取り入れて、減塩調理力をアップさせてくださいね!
ちょっとハードルが高い気がしますね。
でも大丈夫。定番のおうちごはんの中で塩分が高くなりがちなメニューでも、「減塩だしつゆ」を使えばカンタンに減塩ができます。
しょうゆ代わりにお浸しや冷奴にかけるだけでも減塩に。もちろん、煮物や炒め物にも幅広く使えます。
かつおだしのうま味がきいているので、我慢することなく調理の工夫で、満足感を得ながらおいしく減塩ができるのです。
おいしくカンタンなことから取り入れて、減塩調理力をアップさせてくださいね!